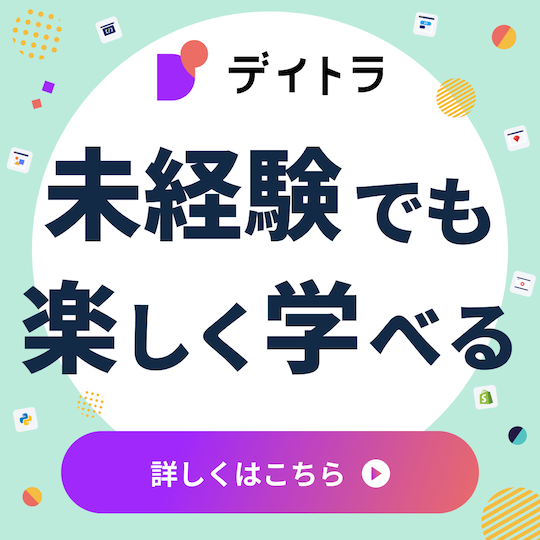Contents
対象読者
- AtCoder初級〜中級
- 「ABC065Bを最短手数で解きたい」「1-based/0-basedの取り扱いでよく迷う」人
問題
問題文
https://atcoder.jp/contests/abc065/tasks/abc065_b
解き方の全体像
- 各ボタンは 次に点灯するボタンが1つ に決まるので、全体は 有向グラフ(各頂点の出次数=1)=functional graph。
- 初期頂点 1 から、矢印に従って 1 → a1 → a[a1] → … と 一直線に辿るだけ。
- はじめて 2 に到達した時の歩数 が答え。
- 2 を含まない サイクル に入ったら、その後は 永遠に 2 に届かない ので -1。
初心者向けたとえ:
蛇口(現在のボタン)をひねると水(光)が次の蛇口に必ず流れる配管が1本だけ繋がっているイメージ。1番の蛇口から水を追っていき、はじめて2番に到着できるか?到着前に同じ所をぐるぐる回り始めたら、もう2番に行けない=-1、というだけ。
ポイント
- 最短を考える必要はありません。道は 1本 なので、「初めて到達=最短」。
- 訪問済み管理(
visited)があると、早めに不可能判定できます(同じ頂点に再訪した瞬間に-1)。 - 1-based の入力を 0-based に直すかどうかを最初に決めて統一。
実装例(最小・速い・わかりやすい)
import * as fs from "fs";
function main(input: string): void {
const [nRaw, ...numsRaw] = input.trim().split(/\r?\n/);
const N = Number(nRaw);
const a = numsRaw.map(Number); // 1-basedの遷移先をそのまま持つ
let steps = 0;
let cur = 1; // 最初は1が点灯(1-basedのまま進める)
while (steps < N && cur !== 2) { // N回たどっても着かないなら不可能
cur = a[cur - 1]; // 0-based添字に合わせて-1
steps++;
}
console.log(cur === 2 ? steps : -1);
}
const inputData = fs.readFileSync(0, "utf8");
main(inputData);
計算量:O(N) 時間、O(1) 追加メモリ
回答の良い点
while (count <= N)の上限で 不可能判定 はできています。- 1-based/0-based の変換(
next = Nums[next]-1)もOK。 - 最短性も正しく満たします(道が1本のため、初到達=最短)。
改善のおすすめ
- 変数名を意味で揃える(
cur/steps)。 visitedを使うと、N 未満で不可能を確定できるケースが増えて実行回数が減ることがあります。
実装例(堅牢版:訪問済みで早期終了)
import * as fs from "fs";
function main(input: string): void {
const [nRaw, ...numsRaw] = input.trim().split(/\r?\n/);
const N = Number(nRaw);
const a = numsRaw.map(Number);
const visited = new Array<boolean>(N + 1).fill(false); // 1..N をそのまま使う
let steps = 0;
let cur = 1;
while (!visited[cur]) {
if (cur === 2) {
console.log(steps);
return;
}
visited[cur] = true;
cur = a[cur - 1];
steps++;
}
console.log(-1); // サイクルに入った(2を含まないループ)
}
const inputData = fs.readFileSync(0, "utf8");
main(inputData);
計算量:O(N) 時間、O(N) メモリ(訪問管理)
サンプルで手計算
- 例:
N=3, a=[3,1,2]
1 → 3 → 2 到達。2回で終了。 - 不可能例:
N=3, a=[1,1,1]
1 → 1 → 1 … 2に着かないので -1。
よくある間違い
- オフバイワン:
a[cur]としてしまい、添字ずれ。→a[cur - 1]に統一。 - カウント開始位置:初期は押していないので 0。最初の遷移で +1。
- 初期チェック忘れ:開始時点は「1が点灯」。いきなり2ではないので、最初の1押しで2に移れるかを確認する。
- 無限ループ:
visited不使用で上限条件を付け忘れ。→steps < Nまたはvisitedで防止。
発展的な実装例(学習用)
- フロイドの循環検出(Tortoise & Hare)
2 に着く前に循環が見つかり、かつその循環が 2 を含まなければ不可能。
ただしこの問題は道が1本なので、単純なvisitedの方が読みやすいことが多いです。 - 到達回数の配列化
「各頂点へ初めて到達するまでの手数」を配列に記録していくと、別の頂点をスタートにした派生問題に応用できます。
計算量とメモリ
- 時間:最大で N 回の遷移
- メモリ:最小実装は O(1)、
visitedを使えば O(N)
まとめ
- 方針:1 から遷移を順に辿り、初めて 2 に到達した時の手数が答え。
- 不可能判定:2 を含まないサイクルに入ったら -1。
- 実装のコツ:1-based/0-based を 最初に決めて統一、上限または
visitedで 無限ループを防止。